適応障害で退職する場合、失業保険をもらうためのコツとは?
適応障害は、職場環境や業務のストレスなどが原因で発生する精神的な障害です。このような状況で退職を決断することは、大変な選択ですが、失業保険を受け取ることで次のステップに進む助けとなります。この記事では、適応障害を理由に退職する場合、どのように失業保険をもらうか、その手順とコツを詳しく解説します。
退職前にすべきこと
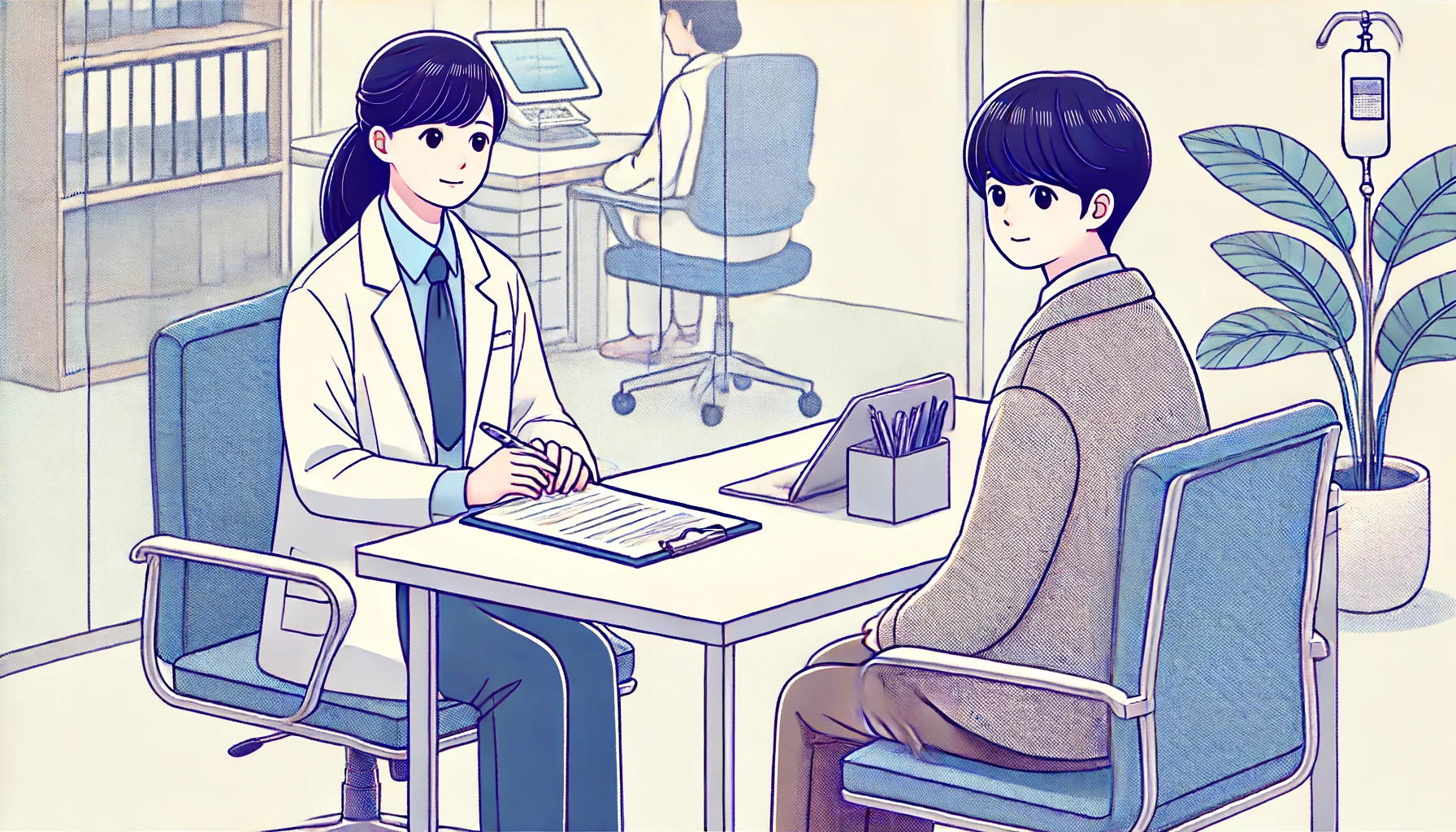
医師の診断書を準備する
適応障害が退職の理由であることを証明するために、必ず医師の診断書を用意しましょう。診断書には、病名と退職が必要な理由が明記されていることが重要です。
この診断書についてですが、適応障害と診断される為には一定期間、医師の診断を受けてきた事が条件に含まれている為、適応障害で退職する場合、適応障害の診断を長年受け続けてきても回復の目途が経っていない条件が必要です。
更に失業保険を貰う上で医師の診断書が必要ですが、その診断書を発行する為にも1か月ほどかかる場合がある為、事前に担当医より診断書が出来るまでどのくらいの期間がかかるのか確認した上で退職の計画を立てた方が良いでしょう。
労働基準監督署に相談
職場のストレスやパワーハラスメントが原因で適応障害を発症した場合、労働基準監督署に相談し、労災申請を検討することも一つの方法です。労災が認められれば、手厚い補償を受けられる可能性があります。
具体的には以下のようなモノがあります。
- 療養補償給付:治療にかかる医療費が支給されます。
- 休業補償給付:休業期間中の給与の一部(平均賃金の60%)が支給されます。
- 傷病補償年金:治療が長期化した場合、傷病補償年金が支給されます。
- 障害補償給付:後遺障害が残った場合、障害補償給付が支給されます。
- 遺族補償給付:労災が原因で死亡した場合、遺族に対して給付が行われます。
その為、適応障害になった原因についてですが、退職前に労働基準監督署で相談し、その後、労災申請の準備を進める流れになります。労災申請には以下の書類が必要です。
- 労災保険給付支給申請書(労働基準監督署で入手可能)
- 医師の診断書(様式第5号)
- 仕事の詳細や業務内容を説明する書類
- 労働条件通知書や雇用契約書のコピー
必要書類を揃えたら、労働基準監督署に労災申請書を提出します。申請書の提出後、労働基準監督署は調査を行い、労災認定の可否を判断します。
労災認定が下りた後は、指定の方法で補償を受け取る事が出来ますので、具体的な支給方法や期間については、労働基準監督署からの案内に従って手続きするようオススメします。
適応障害で退職後の手続き
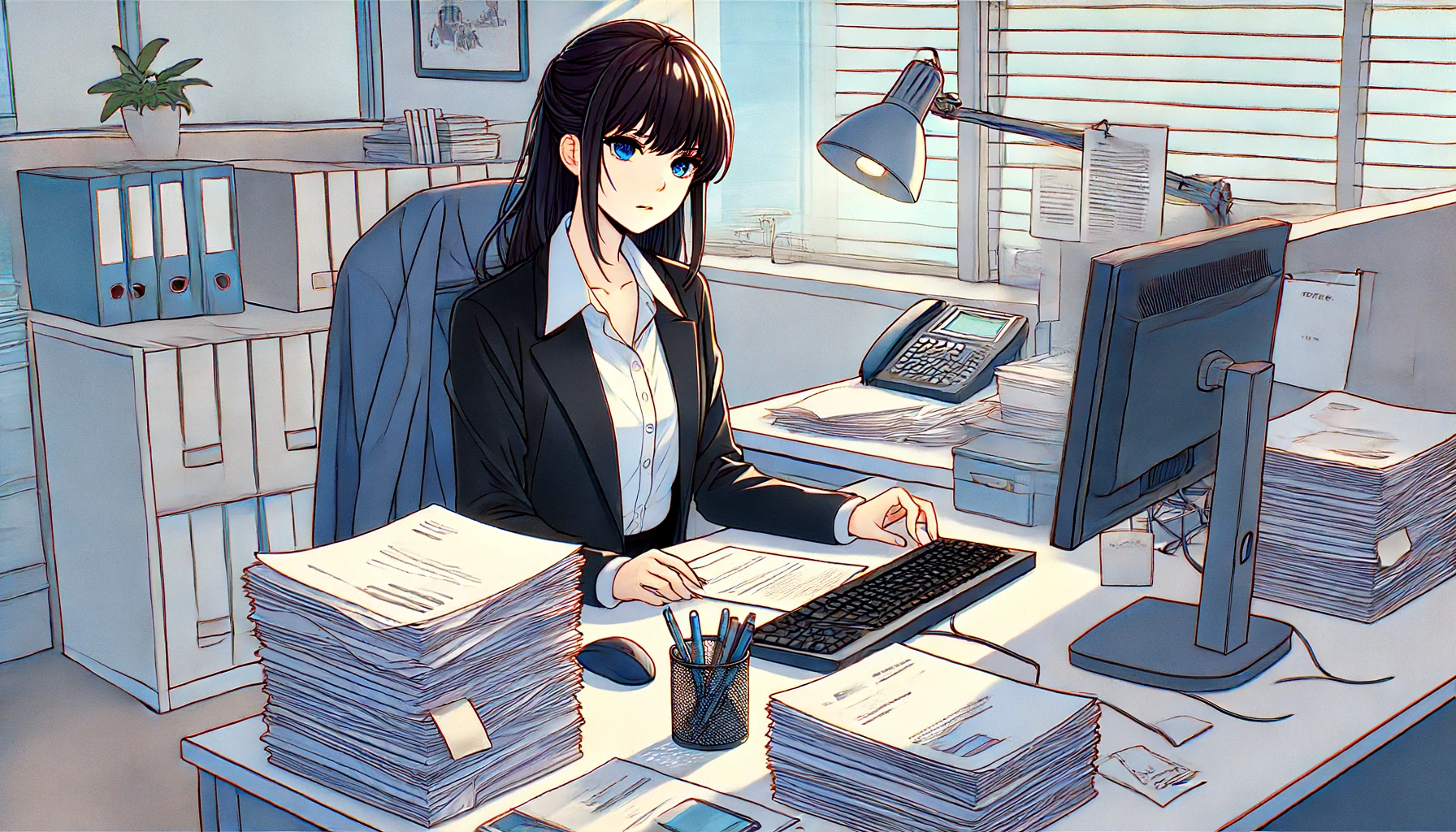
ハローワークに行く
退職後は、速やかにハローワークに行きましょう。失業保険の申請を行うためには、まず「求職の申込み」を行い、失業の状態にあることを証明する必要があります。
必要書類を準備する
以下の書類を用意してハローワークに持参します:
- 雇用保険被保険者証
- 離職票(会社から受け取る)
- 身分証明書(運転免許証など)
- 医師の診断書
特定受給資格者としての認定
適応障害が業務に起因する場合、ハローワークで「特定受給資格者」として認定されることがあります。この認定を受けると、待機期間なしですぐに失業保険を受給できる可能性があります。医師の診断書を提出し、具体的な状況を説明することで、この認定を目指します。
失業保険の計算方法
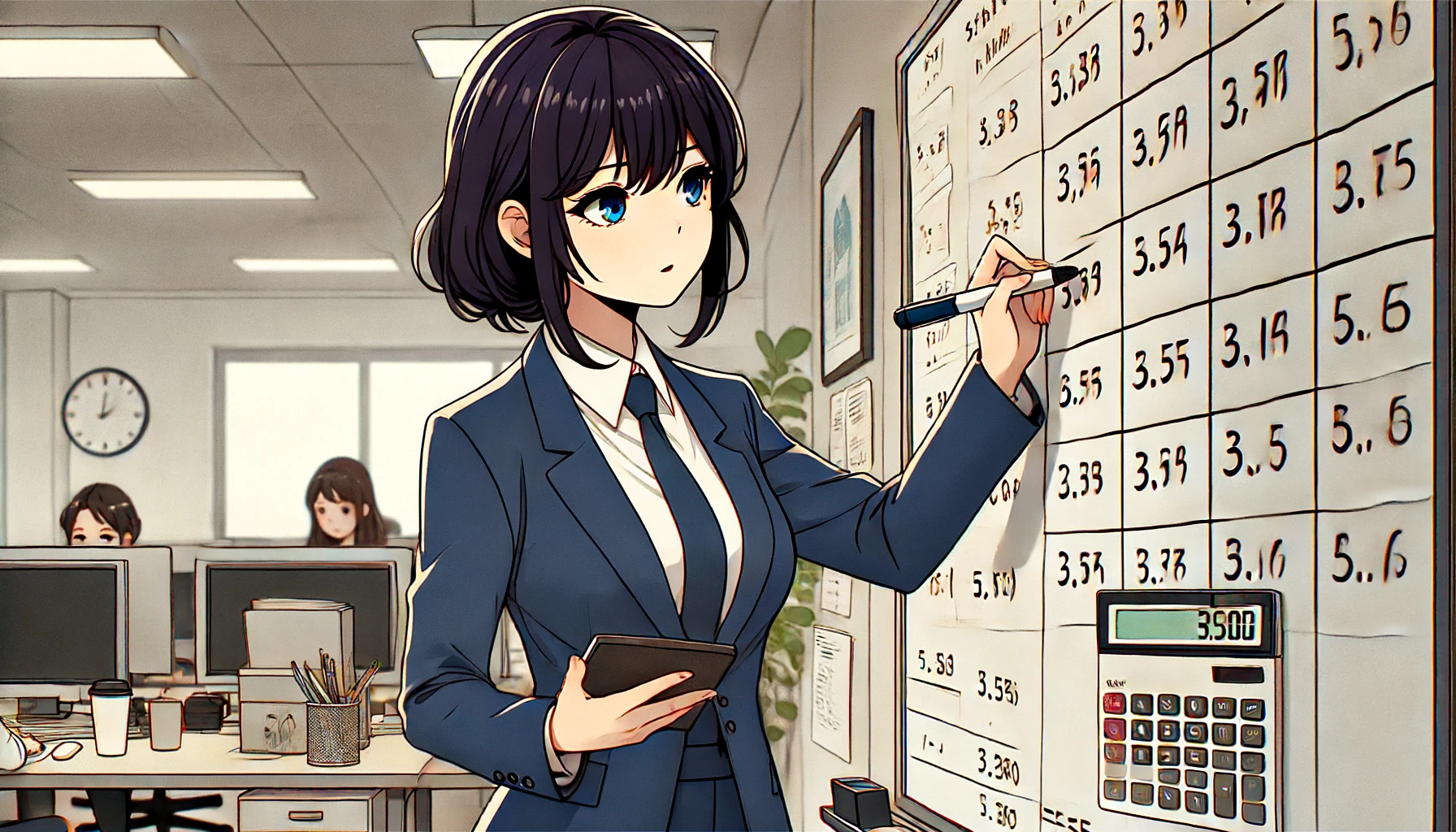
適応障害で退職し、特定受給資格者として認定された場合の失業保険の金額は、以下の方法で計算されます。
基本手当日額の計算
失業保険の基本手当日額は、退職前の6か月間の給与の平均額に基づいて計算されます。具体的には、以下の式を使用します:
基本手当日額=退職前6か月の平均賃金日額×60%
ただし、賃金額が低い場合や高い場合には、以下のような最低額と最高額の制限が適用されます。
例えば30歳未満の場合、
退職前6か月の給与総額が180万円の場合:
180万円÷180日≈10,000円(平均賃金日額)
基本手当日額 = 10,000円 × 60% = 6,000円
上記のように失業手当の1日の手当てが6000円になります。ただし適応障害を理由に退職する場合、障碍者として診断書を持っている場合、障碍者枠として働けるようになる為、失業保険の計算が変わります。
障害者枠での特例
適応障害で退職し、障害者として認定された場合、失業保険の給付条件や期間に特別な配慮が行われます。この記事では、障害者認定を受けた場合の失業保険の受給方法、300日の給付期間、再就職手当について詳しく説明します。
障害者枠での失業保険
障害者枠として認定されると、通常の失業保険よりも手厚い給付を受けることができます。
基本手当日額の計算方法: 失業保険の基本手当日額は、退職前の6か月間の給与の平均額に基づいて計算されます。計算式は次の通りです:
基本手当日額=退職前6か月の平均賃金日額×60%
例:
- 退職前6か月の給与総額が180万円の場合:
- 180万円 ÷ 180日 ≈ 10,000円(平均賃金日額)
- 基本手当日額 = 10,000円 × 60% = 6,000円
給付日数: 障害者認定を受けた場合、失業保険の給付日数は最大で300日間となります。
障害者枠での再就職手当
再就職手当は、失業保険の受給期間中に再就職が決まった場合に支給される特別な手当です。障害者枠での再就職手当についても、通常よりも手厚い支援が行われます。
再就職手当の条件:
- 失業保険の支給を受け始めてから7日間の待期期間が経過していること。
- 失業保険の支給残日数が所定給付日数の1/3以上であること。
- ハローワークの紹介または自己応募による再就職であること。
- 1年以上の雇用見込みがあること。
- 過去3年以内に再就職手当を受けていないこと。
再就職手当の金額: 再就職手当の金額は、次の式で計算されます:
- 支給残日数が所定給付日数の1/3以上、2/3未満の場合: 再就職手当=基本手当日額×支給残日数×60
- 支給残日数が所定給付日数の2/3以上の場合: 再就職手当=基本手当日額×支給残日数×70
具体例:
- 基本手当日額が6,000円の場合
- 所定給付日数が300日で、再就職時点の支給残日数が200日である場合
- 支給残日数が2/3以上(200日)なので、70%が適用されます: 再就職手当=6,000円×200日×70
手続きの流れ
ハローワークでの手続き:
- 退職後にハローワークへ行く:退職後、すぐにハローワークで失業保険の申請を行います。診断書や退職理由を証明する書類を持参します。
- 障害者認定の証明を提出:医師の診断書など、適応障害であることを証明する書類を提出します。
- 特定受給資格者としての認定:障害者としての認定を受け、特定受給資格者として申請します。
適応障害で退職し、障害者として認定されると、失業保険の給付日数が最大で300日間となり、再就職手当も手厚く受けることができます。失業保険の基本手当日額は給与の60%となり、再就職時に早期再就職手当を受け取ることで、経済的な安定を図ることができます。ハローワークでの手続きを確実に行い、適切なサポートを受けましょう。
失業保険を受け取るためのコツ
定期的な活動報告
ハローワークでの失業保険の申請後、定期的に求職活動の報告を行う必要があります。これにより、失業保険の受給資格を維持します。
職業訓練の活用
失業保険の受給期間中に職業訓練を受けることで、スキルアップを図りながら失業保険の給付を延長できることもあります。ハローワークの職業訓練プログラムを活用することを検討しましょう。
まとめ
適応障害を理由に退職する場合、失業保険を受け取るためにはいくつかのステップがあります。医師の診断書を用意し、ハローワークでの手続きを正確に行うことで、特定受給資格者としての認定を受けやすくなります。また、定期的な活動報告や職業訓練の活用も重要です。困難な状況ではありますが、適切な手続きを行い、失業保険を受け取って次のステップに進むための支援を受けましょう。


