適応障害を理由に塾講師を退職し、その後再び教育現場に立つ事を目指す皆さん、どのように行動すべきか迷っているのではないでしょうか。
私自身、適応障害で教育現場を去った経験があります。退職後の失業保険の手続きや治療、そして退職そのものへのショックなど、思い描いた通りの結果には至りませんでした。適応障害が悪化し、再就職への道は険しいものでした。
しかし最終的には再び教壇に立つ事が出来、適応障害も徐々に改善されました。適応障害を抱えたままの再就職は大変な部分も多いですが、退職後の対応を誤ると、後に取り返しがつかない状況を招く事もあります。
このような経験を通じて得た知見を、これから再就職を考えている皆さんと共有したいと思います。私の体験談と、どのように再就職に成功すればいいのかを、本記事で詳しく説明したいと思います。
適応障害が原因で退職した塾講師がすべきアピールとは?

適応障害で退職した塾講師が再就職で成功する為の重要な要素は、いくつか存在します。特に焦点を当てるべきは次の3つのポイントです。
- 面接時に適応障害による退職経験をどのように伝えるか?
- 再就職後、適応障害の再発リスクをいかに防ぐか?
- 適応障害をマイナスと捉えず、ポジティブに捉える方法
多くの塾講師が再就職の道を探る中で、面接時に退職の原因や適応障害についてどのように説明し、自分が教育の現場で再び活躍出来る人材である事をどうアピールすれば良いのか、直感的に答えが見つからず迷う場面があります。
適応障害を持ちながら再び教育の現場で成功を収める為には「適応障害による退職の正確な理解と説明」「適応障害の再発防止策」そして「適応障害を持つ塾講師が教育現場で活躍出来る根拠」の3つを明確にする事が重要です。これらを用意する事で、適応障害を持つ塾講師自身が自信を持って再就職活動に臨む事が可能となります。
適応障害で退職した塾講師の採用アピール:職場環境が原因だったとするアプローチ
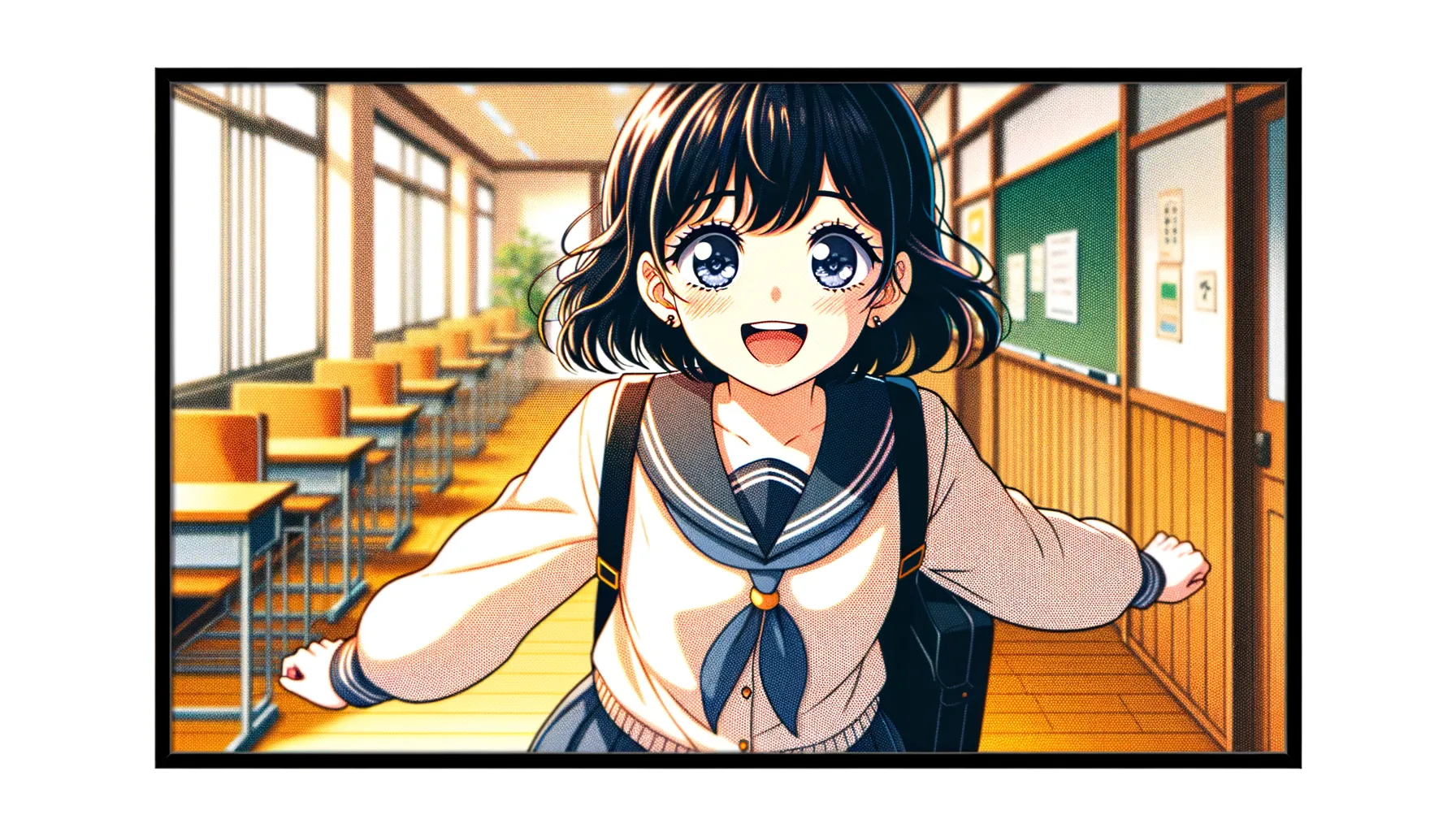
教育業界での面接では、適応障害で退職したという事実を説明する際には慎重さが求められます。そこで重要なのは、自己の働きぶりではなく、職場環境が原因であったとするアピールです。
塾講師として働く上で、過度な業績目標や長時間労働、生徒や保護者からのプレッシャー、そして教育ノルマといった要素が適応障害の原因になる事があります。これらの問題は、個々の教師の努力ではなく、塾の経営スタイルや体制に起因するものです。
私自身のケースでは、塾の業績目標が非現実的であり、その達成の為に過度な時間とエネルギーを要求される環境に置かれていました。また保護者からの高い期待と厳しい評価、そして生徒の進学成功へのプレッシャーが重なり、それらが適応障害を引き起こす原因となりました。
新しい職場では、教師の働き方や教育方針に対する理解と配慮、そして適切な業績評価と労働時間管理が求められます。これらを実現する職場環境を持つ塾に就職したいと考えています。
このような経験を説明する事で「私が適応障害を患った原因は、前職の職場環境にありました。新しい職場では、より健全な教育環境とバランスの取れた労働環境を求めています」というメッセージを伝える事が出来ます。これにより、適応障害での退職理由と志望動機を一緒に伝える事が可能となり、より有利な採用評価を得る事が期待出来ます。
適応障害で退職した原因が塾講師本人にあると疑われた際の対処法
教育業界の中で、塾講師として働いていた場合、適応障害で退職したときの面接で「実はおそらくあなた自身の対応力不足が原因では?」と疑われる事があります。
それは、面接官が「授業の進行や生徒とのコミュニケーションの調整、または保護者との対話をうまく行えなかったのでは?」といった問題解決能力を問う為に、あえてそう問う事があります。
実際には、塾講師が適応障害に陥る原因は、人間関係、授業の進行、生徒や保護者とのコミュニケーション、過酷な労働時間など、多岐にわたります。それらすべてが講師本人の責任ではなく、組織側の問題も大いに関与しています。しかし面接では自己PRの場として、これらの問題にどのように対処し、乗り越える力を身につけたかをアピールする事が求められます。
具体的には「生徒の学力差に対応する為の授業計画を提案しましたが、校舎長から一律のカリキュラムに従うよう指示され、自由な教え方が出来ませんでした。しかしそれでも私は生徒一人一人に寄り添う指導を心掛け、その結果、生徒の学力向上につながる事が出来ました」といった具体的な事例を話す事が求められます。
また「保護者とのコミュニケーションは、教育の現場において重要な要素です。しかし私が働いていた塾では、保護者からの不満が直接塾講師に押し付けられる環境で、管理職の対応不足により適応障害に陥りました」というように、自身の経験をもとにした具体的な事例を挙げる事で、適応障害に至った原因が組織側にあった事を示す事が出来ます。
以上のように、適応障害で退職した原因が自身にあると疑われた場合でも、具体的な事例を用いて自身の対応策や問題解決能力をアピールする事で、面接官に対して自己の価値を訴える事が可能です。その際、自身の経験を振り返り、事例を具体的に説明する事で、その信憑性を高める事が求められます。
適応障害で退職した塾講師の成功する再就職戦略
適応障害で退職した塾講師の中には「塾や上司が原因で退職に至った」と再就職の面接で訴える人がいます。しかしその訴えだけでは同情を得るだけで、再就職への道は開けません。私自身もそうでした。
難しいのは、教育現場に問題があったとしても、それだけではあなた自身に問題がないとはならないという事です。私がここで提案するのは、自身の問題解決能力に問題がなく、かつ教育現場が原因で改善されなかった事実を明確に述べる事です。それにより「現場を改善するよりも環境を変える方が良い」と、適応障害を解決する為の再就職が適切な手段として受け入れられやすくなります。
私自身の経験から、以下のような原因が挙げられます。
- 教え子が途中で辞める事があり、引継ぎが無しでかつ生徒増加が無かった為、適応障害になりました。
- 教材の内容が保護者や学校との意見のすれ違いで、スケジュールが遅れたり、急な修正が頻繁に起こり、適応障害になりました。
- 上司が新しい教育方針を突然提案し、余計な業務を増やした上、やれば出来ると無理を強いた結果、適応障害になりました。
など、生徒、保護者、上司などが原因で改善の見込みがなく、適応障害が悪化して結果的に退職する事になった経緯を具体的に説明出来れば、再就職の面接が通りやすくなるでしょう。
適応障害でも長く教えられる塾講師になる方法

塾講師の世界でも適応障害を理由に退職を決意する人がいます。「塾で配慮してほしい事は何でしょうか?」と、適応障害による不便を軽減するにはどうすればいいのかを理解する事が重要です。
適応障害があるからといって教えられないわけではありません。しかしそれを理解してもらう為には、適応障害があっても教える事が出来るという自己アピールが必要となります。
適応障害が発症してしまう原因が仕事の量であれば、塾講師の場合、オンライン教育ツールを活用する事で、一度に多くの生徒に教える事が出来、教職の負担を軽減する事が出来ます。
または、クラスの管理が難しい場合は、各生徒の進捗状況を共有する為の進捗管理ツールを活用する事で、全体の管理がスムーズに行えます。
その為、適応障害になる原因を極力減らす為、その原因を取り除くアピールをする事が求められます。教える事への情熱と、それを支える為の工夫を自己アピールに盛り込む事で、適応障害でも長く働ける塾講師となれる可能性が広がります。
「なぜ当塾が適応障害を予防する教育現場だと考えたのか?」と問われた際の対策法
ただ単に教育現場の改善を行えば良いとも考えられますが、全ての塾がその実現に至るわけではありません。その為、面接で志望動機を述べる際に「なぜ当塾が適応障害を防げる教育現場であると思ったのか?」と問われ、途方にくれる事もあるでしょう。
適応障害を予防出来る教育現場でなければならない以上、志望先の教育環境が異なると主張出来るように準備しておく事が必要です。しかしその塾で働いた経験がなければ、どう答えれば良いのか分からないかもしれません。私自身の経験から言いますと「口コミサイトを参考にし、あなた方の塾が最適だと判断しました」と述べて乗り切る事が出来ました。
転職をサポートするサービスの中には、実際にその塾で働いた経験のある人々の口コミが掲載されているものもあります。
私自身、そのようなサービスを試した結果「休憩時間が十分にある」と書かれていましたが、実際の口コミを見ると「業務時間が削減され、結果的にストレスが増加した」という内容や「過度な業務量により、上司からの圧力が強かった」といったコメントが多く見られ、適応障害を抱える人が転職すべきではない塾である事が明らかとなりました。
このように、教育現場の内部情報を詳細に書かれた口コミは、転職を検討する際に、不適切な労働環境かどうかを判断するのに非常に役立ちます。
また志望動機についても「口コミサイトの評価が高かったから」と述べる事で、適応障害を持つ自分に適している塾であるとともに、評価が高いと記されていれば、それが妥当な志望動機となります。ですから、口コミサイトを活用して志望先の選定や志望動機の作成を行う事は、有効な手段と言えるでしょう。
適応障害をプラスに活用する塾講師の対応方法
適応障害は一見すると教育職におけるデメリットのように思えますが、実はそれを逆手に取り、塾講師の仕事に役立てる事が可能です。
適応障害を患っているからこそ「すいません、授業の進行を記録に残させてください」と生徒や保護者に伝える事で、授業の内容や進行状況を正確に把握する為の記録をつける事が可能になります。
特に塾講師の場合、生徒一人ひとりの理解度や進度が異なる為「言った、言わなかった」「教えた、教えてない」などの問題が生じてしまう事があります。しかし適応障害を理由に授業の進行記録をつける事で、こういった問題を未然に防ぐ事が可能になります。
また適応障害を持っている事を逆手に取って、授業の進行記録をつける事で、生徒や保護者に対しても自分の授業方法や教え方の透明性を高める事が出来ます。これにより信頼関係を築く事が出来、塾講師としての評価向上にも繋がります。
更に、授業の進行記録をつける事で、生徒の理解度や進度、課題の状況などを具体的に把握しやすくなります。これにより、生徒の学習計画や指導方法をより適切に見直し、改良する事が容易になります。
適応障害を持つ事が教育職におけるデメリットだと感じてしまうかもしれませんが、適応障害を持つからこそ出来る対応やアプローチが存在します。適応障害を持つ塾講師として、自分の強みとして活用し、より良い教育環境を作り出しましょう。
適応障害で退職した塾講師の再就職成功への道

適応障害を理由に退職した塾講師が、再就職に成功する為には、以下の点に注意して進める事が有益です。
- 自身の適応障害が改善の余地があったとアピールする
- 志望動機として、口コミサイトで評価が高い塾を選ぶ
- 適応障害を逆に長所だと感じさせるアピールを用意する
適応障害で退職した以上、失業保険期間は可能な限り長く取得すると良いです。
精神科医からの提案で退職するほど適応障害が深刻であれば障がい者手帳を申請し、失業保険の期間を一般の3カ月から10カ月に延ばすと良いと言われました。長期間精神科医に通院していた場合、障害年金も受給出来る可能性がある事も後に知りました。
適応障害が原因で退職した場合も、日本には障がい者に対するさまざまなサポートがある為、退職後の期間を活用して手続きをしてみる事が有益です。
ただし障がい者枠で転職活動を行う場合、障がい者専用の転職サイトの場合、契約社員の求人が多く、正社員の求人が少ない事を知りました。ですので仮に大手の正社員を障がい者枠で目指したいのであれば、直接塾のホームページから応募した方が良いでしょう。
正社員採用は狭き門である為、面接では自分がどのように生徒の成績を上げる事が出来るか示す事が大切です。適応障害を逆手にとって業務に対する配慮や理解を深める事が出来る話をするなど、障がい者ならではの立ち回りが必要です。
以上が私自身、体験した適応障害で退職しても直ぐ再就職する事が出来る塾講師のノウハウです。このような工夫を行う事で適応障害を理由に退職した塾講師でも再就職の成功確率が上がるので、皆様の再就職の成功を心より願っております。


