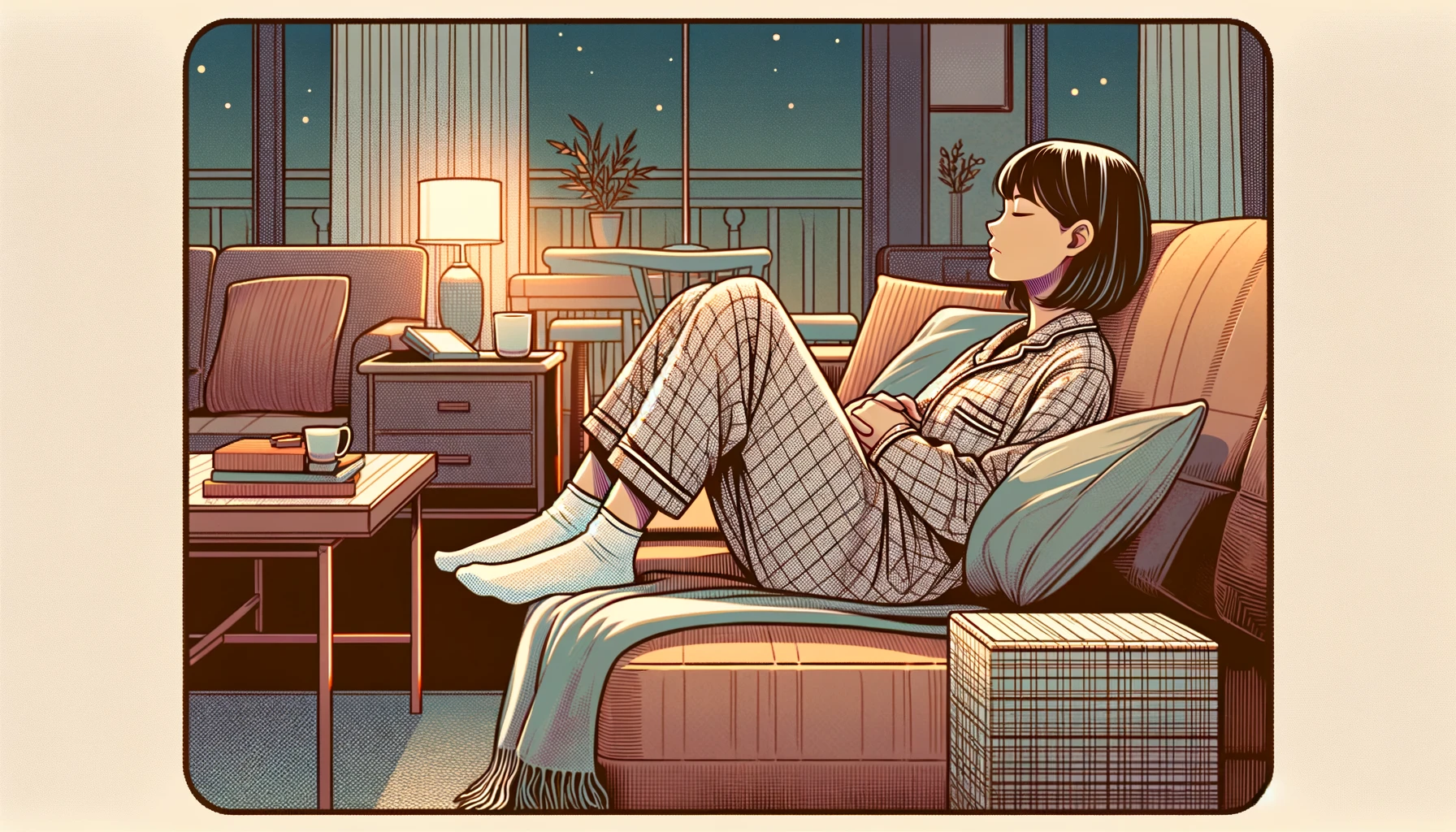適応障害と診断されたのを機に今の職場で働けないと思い、退職を考える人は少なくないと思われます。しかし適応障害を持ちながらも会社の方から引き止められる事も少なくありません。
その場合、働き続けても大丈夫なのか?また退職したい理由として職場にいる人から適応障害だと知られるのが嫌だという理由もあり、更に引き止めてくる上司に対しても信用出来ないケースもあると思われます。
その場合、どのように引き止めてくる人を説得し、退職すべきか判断すれば良いのか?この記事では適応障害で退職したいのに引き止めに合った場合の対処法をITエンジニアや看護師の2人の具体的な体験談を交えながら詳しく解説します。
ITエンジニアの体験談:適応障害で退職を引き止められた場合

ITエンジニアのAさんは、長時間労働と厳しい納期に追われる日々を過ごしていました。ある日、心身の不調を感じ、精神科を受診したところ適応障害と診断されました。Aさんは退職を決意し、上司にその旨を伝えましたが、会社から引き止められました。
引き止めの理由と対策
会社は、Aさんのスキルと経験がチームにとって重要だと考え、勤めながら適応障害を治すよう退職を引き止めました。上司からは、以下の提案がされました:
- 休職制度の利用:一定期間の休職を取る事で、心身を休める時間を確保する。
- 職場環境の改善:仕事量の調整や業務内容の変更を検討する。
- フレックスタイム制の導入:柔軟な働き方を導入し、Aさんが自身のペースで働けるようにする。
Aさんは一度はこれらの提案を受け入れ、休職を取って療養し、職場環境の改善とフレックスタイム制の導入により、しばらくは症状が改善されるように見えました。
ただ問題だったのは周囲の同僚からの軋轢です。
当初、上司は適応障害は個人情報であり、同僚に話さないという判断をしました。
その結果、同僚たちはAさんが特別扱いされていると感じ、Aさんとの間に距離が生まれてしまいました。Aさんが特別な配慮を受けている事について不満や疑念を抱く同僚もおり、職場での協力体制が崩れてしまいました。
結果、Aさんの症状は人間関係が原因で再び適応障害が悪化し、職場環境に対する不信感も高まりました。最終的にAさんは職場での信頼関係が回復する見込みがないと判断し、再度退職を決意しました。
看護師の体験談:適応障害で退職を引き止められた場合

看護師のBさんは、夜勤が続く過酷な勤務環境で働いていました。夜勤の連続や過度な患者対応、チームリーダーとしての責任など、ストレスが蓄積し、適応障害を発症しました。精神科を受診した結果、適応障害と診断され、Bさんは退職を決意し、上司にその旨を相談しましたが、病院から引き止められました。
引き止めの理由と対策
病院は看護師不足の為、Bさんの退職を避けたいと考えました。上司からは、以下の提案がなされました:
- シフトの調整:夜勤を減らし、日勤中心のシフトに変更する。
- メンタルヘルスケアの導入:カウンセリングの受診を促し、メンタルヘルスケアを強化する。
- サポートグループの参加:同じような悩みを持つ同僚とのサポートグループに参加し、支え合う環境を作る。
Bさんはこれらの提案を一度は受け入れ、シフト調整とメンタルヘルスケアを導入する事で症状の改善を図ろうとしました。しばらくの間、日勤中心のシフトで体力的な負担が軽減され、カウンセリングを受ける事で精神的にも少しずつ回復を感じました。またサポートグループへの参加は、同じ境遇の同僚との交流を通じて精神的な支えとなりました。
しかし上司は適応障害に関する情報リテラシーが欠如しており、Bさんの個人的な状況を他の同僚に話してしまいました。
その結果、Bさんの適応障害に対する偏見や誤解が生じ、職場での立場が微妙になってしまいました。
同僚たちとの間に距離が生まれ、チームでの協力体制が崩れ、仕事を分担してもらう事が難しくなりました。Bさんの症状は再び悪化し、職場環境に対する不信感も高まりました。最終的に、Bさんは職場での信頼関係が回復する見込みがないと判断し、再度退職を決意しました。