適応障害をきっかけに職を辞め、図書館助手としての再就職を考える時、どのようなアプローチが最適なのか、明確な答えはないかもしれません。
私自身、適応障害を理由に勤めていた会社を辞め、再就職活動に専念した経験があります。しかし失業保険の手続き、治療、そして退職に伴うショックなど、様々な困難に直面し、適応障害は一層深刻化しました。
それでも、最終的には新たな職場を見つけ、適応障害も徐々に改善しました。適応障害を抱えて再就職を目指す道程は決して容易ではなく、間違った方法で立ち向かうと、取り返しのつかない結果を招く事もあります。
そこで、私の経験がこれから再就職活動に挑む方々の参考になる事を願い、この記事で私が経験した事、そしてどのように図書館助手として再就職を成功させる事が出来たのかを共有したいと思います。
適応障害が原因で退職した図書館助手がすべきアピールとは?
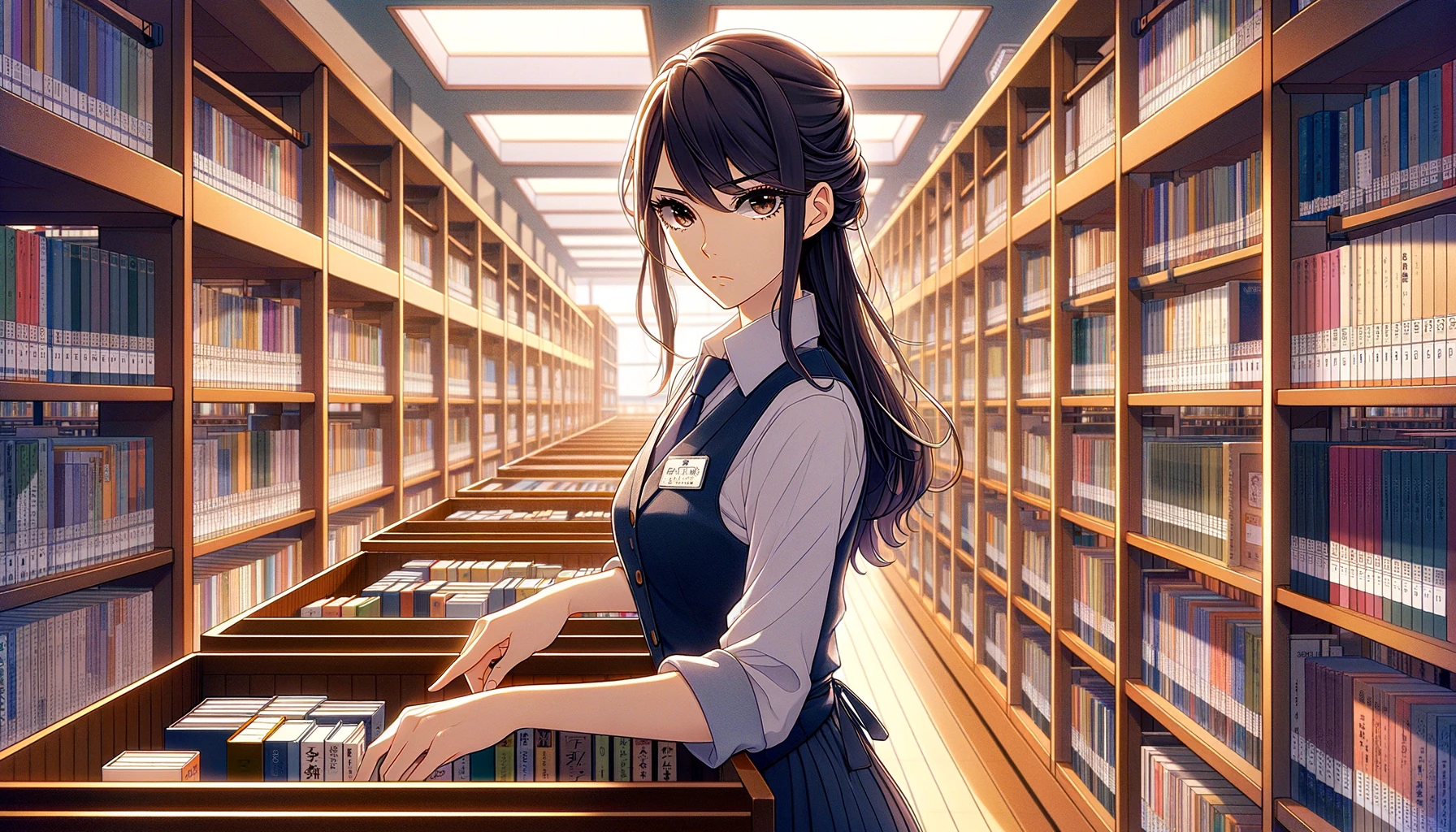
適応障害で退職した図書館助手が再就職で成功する為のポイントはいくつかあるかもしれませんが、以下の3つを特に心に留めておくと良いでしょう。
- 適応障害で退職した経緯をどのように面接官に伝えるか?
- 就職後、適応障害の再発を防ぐにはどうすべきか?
- 適応障害をマイナスに感じさせない面接のやり方
私自身も多くの図書館への応募中に、面接で退職の原因や適応障害についてどのように説明し、自分がしっかりと仕事が出来る人間である事をどうアピールすべきか、その良い答えをすぐに思いつく事が出来ずに困った経験があります。
適応障害を抱えながらも成功する為には「退職の理由の説明」「適応障害の再発防止策」そして「適応障害を持つ自分が図書館助手としてどう活躍出来るか」をきちんと準備しておく事が重要です。
適応障害で退職してるのにマイナスにならない図書館助手の退職理由

面接で適応障害で退職した理由を説明する場合、印象が悪くなる事は避けたいものです。その為、自身ではなく職場環境が原因である事を強調する事が有効です。
図書館助手の仕事では、膨大な量の書籍を短期間で整理したり、様々な読者の要望に対応したりする事が求められます。私の場合、長年使用されてきた図書管理システムの更新が原因で適応障害を引き起こしました。
新しいシステムの導入に伴い、全ての図書を再度登録する作業が必要でした。しかしその作業量と短期間での完成を求める職場の環境が原因で、日々の仕事がストレスとなり、適応障害に至りました。
この経験がある為、「新しい職場では職員全員が情報共有を行い、一人に大きな負担がかからないような環境に就職したい」と面接で説明すれば、退職理由や志望動機を伝える事が出来ます。
適応障害で退職した経験は、新しい職場での適応能力を問われるかもしれませんが、それが図書館助手としての職務に対する理解と向上心につながる事を強調すれば、マイナスにはならないでしょう。
退職した原因が職場ではなく、自分自身にあるのでは?と面接で疑われないようにする方法
転職活動では上記のように自分の悪い部分を極力話さないよう頑張るべきだと思いますが、それでも面接官の中には「あなたに原因があるのでは?」と疑われてしまう事があります。
私自身、経験した事があるのですが、図書館業務の大変さを説明しても自分でこの問題を解決しようとしなかったの?と聞かれる事があります。
事実「図書管理システムの更新や職場内でのチームビルディングの取り組みで改善出来なかったのですか?」と改善案を向こうから提案され、改善出来なかった理由について説明しないといけない場面がありました。
本当に改善出来ないかどうかはやってみないと分かりませんが、ただ私の現場では私だけでなく、他の方がの提案も組織内の保守的な考え方により実現不可能であった事を説明しました。
図書館助手としての業務は一見穏やかに見えるかもしれませんが、その特有の課題と圧力は想像以上に大きいものがあります。私の経験では、図書館内での人間関係の複雑さ、資料管理の細かな要求、そして訪問者からの高い期待がストレスの主な源でした。
特に資料の整理整頓やデジタル化プロジェクトの進行において、組織内の協力不足が問題となりました。私は改善策として、より効率的な資料管理システムの導入や、職員間のコミュニケーション強化を提案しました。しかしこれらの提案は固定化された慣習や予算の制約を理由に上層部から却下されました。
この結果、改善が見込めない環境の中での過剰な労働と精神的圧力が私を追い詰め、適応障害を発症することになりました。私のケースでは、環境の改善を試みたものの、組織全体の抵抗により、その試みは失敗に終わりました。
このような改善を幾つか出し、そして私以外にも改善を提案したのですが、受け入れてもらえず退職する人が出てきました。と言えれば自分ではなく、人が離れやすい職場が原因と面接官は判断してくれます。
適応障害が原因で退職する図書館助手の為のアドバイス
適応障害で退職した経験を持つ図書館助手の中には「職場環境や上司が原因で退職を余儀なくされた」と面接で訴える方がいます。しかしそのような訴えだけでは同情を得るだけで、再就職にはつながりません。私自身もその一人でした。
障がい者支援の一環として、確かに職場に問題が存在していたとしても、それが自身に問題がないという事にはなりません。ここで私が提案するのは、自分自身の問題解決能力が確かである事をアピールし、更に職場環境が原因で改善出来なかった事実を語る事です。そうすれば、「職場環境を改善するより環境を変える方が適応障害の解決に繋がる」という観点から転職が有効な手段と捉えられやすくなります。
私の場合、図書館の組織運営に問題があると主張しましたが、他にも以下のような原因がありました。
- スタッフが予告なく休職を取った為、引き継ぎがなく人手不足になり、適応障害になりました。
- 図書館の運営方針が頻繁に変わり、スケジュールが遅れたり、急な業務変更が頻繁に起こり、適応障害になりました。
- 上司が新たなプロジェクトを提案し、余計な業務が増え、それが適応可能な範囲を超えてしまった結果、適応障害になりました。
このように、スタッフの問題、運営方針の問題、上司の問題などが原因で、改善の見込みがなく適応障害が悪化し、結果的に退職する事になった経緯を説明出来れば、再就職の面接も通りやすくなるでしょう。
次の職場でも適応障害を理由に退職しない為の図書館助手向け対策

適応障害が原因で退職を考えてしまった図書館助手の悩みとして「次の職場では絶対、適応障害によるトラブルは起こさないってどうやって言えばいいの?」というのがあります。
志望動機、ならびに転職後の活動についての質問も面接では高い確率で聞かれますので、その対策と改善策について解説します。
自分の過去の経験を振り返るにあたり、業務量が原因で適応障害になる場合、業務負担を減らす為の工夫が必要です。「図書の整理や配架」や「資料の検索」などの業務は、自動化システムを使って効率化する事が可能です。図書館管理システムを活用し、手作業を減らす事で、心理的なストレスを軽減する事が出来ます。
また管理業務が適切に行えていない場合、管理ツールを活用する事が有効です。ツールを使って業務の進捗状況を共有し、全体の進行を把握する事で、混乱を防ぎ、スムーズな業務運営を実現します。
適応障害の原因を極力減らす事で、心地よい働き方を実現し、適応障害による退職を防ぐ事が出来ます。
「なぜ当図書館では適応障害が発症しないと思ったのですか?」と問われた際の対処法
職場環境を改善し、適応障害を予防するのが最良の方法ですが、すべての図書館がその理想に近づけているわけではありません。その為、面接で志望動機を問われ、「なぜ当図書館ではその適応障害が発症しないと思ったのですか?」と質問され、どのように答えるべきか困る事があるでしょう。
適応障害を予防する環境で働く事が必要である以上、志望先の職場環境が他と異なると言えるようにする必要があります。しかしその図書館で一度も働いた事がない場合、どう答えるべきかを知るのは困難です。私自身もそのような場面に遭遇し、「口コミサイトを参考にし、皆様の図書館が最も適応障害が発症しづらいと思ったからです」と回答する事で乗り越えてきました。
転職活動をサポートするサービスには、実際にその図書館で働いた事がある人々の口コミが掲載されているものがあります。私もこれらのサービスを利用し、求人広告には「労働時間が短い」と記載されているものの、口コミを見ると「勤務時間が短い為に仕事が終わらない、上司からの過度な圧力がある」といったコメントが多く見受けられました。これらの情報から、適応障害を抱えている人が転職すべきでない図書館であると認識する事が出来ました。
このように、職場の内部事情について書かれたコメントは、転職をした際に労働環境が劣悪であるかどうかを判断する上で非常に参考になります。
そして、志望動機として「口コミサイトの評判が良いから」と言えば、適応障害を持つ自分に適した図書館であると同時に、評判が良いと評価されていれば志望動機として適切です。その為、口コミサイトを利用して志望先の選定や志望動機の作成を行うのもおすすめです。
適応障害を図書館助手の仕事に活かす方法
あなたが適応障害を持つ図書館助手で、その事を職場に対して明確に伝える必要がある場合、デメリットとして感じるかもしれません。しかし適応障害を職場でのプラスに変える事も可能です。
適応障害を理由に「申し訳ありませんが、記録を取らせていただけますか?」と頼む事で、会議の記録係を務め、認識の違いを防ぐ事が出来ます。このように適応障害を逆手に取り、記録を取るという配慮を求める事で職場の円滑な運営を支える事が出来ます。
図書館での業務においても、「誰が何を言ったか」を明確にしないと、責任の所在が曖昧になり、問題が生じやすいです。記録を残す事で、このような問題を防ぐ事が可能です。
しかしすべての人が記録を取る事を理解し、受け入れてくれるわけではありません。「口頭で十分だ」「なぜ記録を取る必要があるのか」と疑問に思う人もいます。
そんな時こそ、適応障害を持っている事を伝え、配慮を求める事で、記録を取る許可を得る事が出来ます。これにより、図書館の運営がスムーズになり、問題が起きたときも明確な記録を元に対応する事が出来ます。
もし、適応障害をデメリットとして見てしまう人と出会ったときは、上記のように適応障害を仕事に生かす具体的な例を挙げて、適応障害を持つ自分が図書館助手として十分に働く事が出来る事を伝える事が重要です。
適応障害で退職した図書館助手の再就職成功への道

適応障害を理由に退職した図書館助手が、再就職に成功する為には、以下の点に注意して進める事が有益です。
- 適応障害が原因で退職した事実があっても、改善の余地があったとアピールする
- 志望動機として、口コミサイトで評価が高い図書館を選ぶ
- 適応障害を逆に長所だと感じさせるアピールを用意する
適応障害で退職した以上、失業保険期間は長いほど良いと思います。精神科医からの提案で退職するほど適応障害が深刻であれば障がい者手帳を申請し、失業保険の期間を一般の3カ月から10カ月に延ばすと良いと言われました。私自身、長期間精神科医に通院していた場合、障害年金も受給出来る可能性がある事も後に知りました。
適応障害が原因で退職した場合も、日本には障がい者に対するさまざまなサポートがある為、退職後の期間を活用して手続きをしてみる事が有益です。
ただし障がい者枠で転職活動を行う場合、私が確認した所、障がい者専用の転職サイトの場合、契約社員の求人が多く、正社員の求人が少ない事を知りました。ですので仮に大手の正社員を障がい者枠で目指したいのであれば、直接図書館のホームページから応募した方が良いでしょう。
正社員採用は狭き門である為、面接では自分がどのように成果を上げる事が出来るか示す事が大切です。適応障害を逆手にとって仕事を有利に進める事が出来る話をするなど、障がい者ならでの立ち回りが必要です。
以上が私自身、体験した適応障害で退職しても直ぐ再就職する事が出来る図書館助手のノウハウです。このような工夫を行う事で適応障害を理由に退職した図書館助手でも再就職の成功確率が上がるので、皆様の再就職の成功を心より願っております。


