適応障害で職場を離れた後、再びデイケアスタッフとして職に就く方法について、皆さんはどのように対処すれば良いのか迷うかもしれません。
私自身、適応障害を理由に仕事を辞め、その後で転職を試みましたが、失業保険の手続きや治療、そして退職したという事実への衝撃など、思い通りの結果にはなりませんでした。適応障害は一層深刻化しました。
しかし最終的には再びデイケアスタッフとして働く事が出来、適応障害も徐々に改善しました。適応障害を抱えていると、再就職は困難で、退職後の対応を誤ると取り返しのつかない事態になります。
その為、私の経験がこれから転職を考える皆さんの参考になればと思い、この記事で私の体験と、どのようにデイケアスタッフとして再就職するかの方法について共有したいと思います。
適応障害で退職したデイケアスタッフが再就職に成功する為の戦略
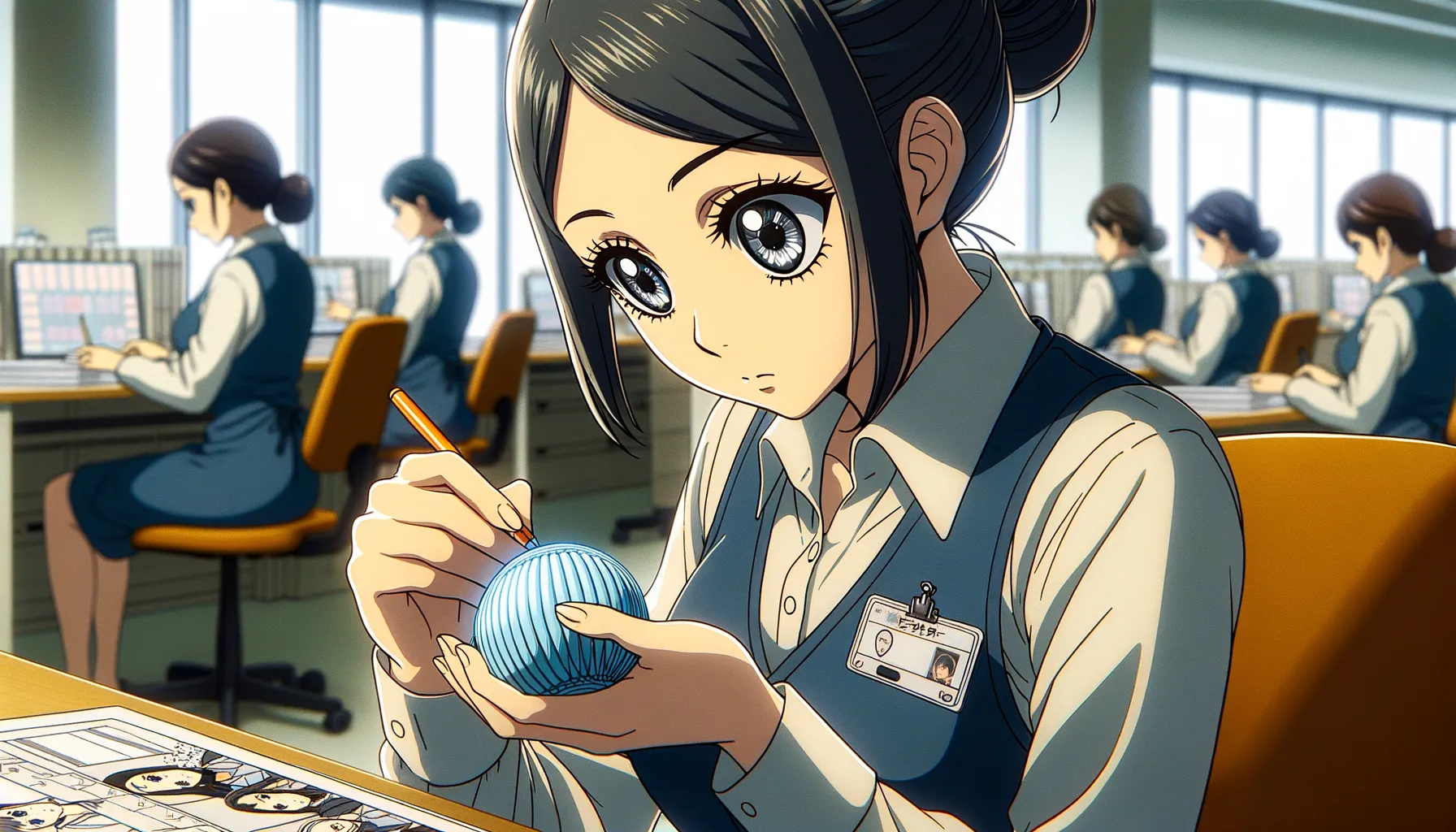
デイケア業界で適応障害を経験し、退職を余儀なくされたスタッフが再就職に成功する為の戦略は、多岐にわたります。特に重要なポイントとして、以下の3つを挙げる事が出来ます:
- 適応障害による退職の経緯をどのように面接官に伝えるか?
- 再就職後、適応障害の再発リスクをどのように減らすか?
- 適応障害をマイナスと感じさせない為の表現方法
デイケアスタッフとしての専門性をアピールしつつ、適応障害という個人の経験をどう説明するかは、再就職の成功に大いに関与します。時には思いがけず、自身の適応障害の経験をどう表現すべきかに悩む瞬間もあるでしょう。
適応障害を経験しながらも再就職に成功する為には「退職の理由の説明」「再発予防策」「適応障害を抱えつつ、デイケア業界で活躍出来る理由」の3点について納得のいく答えを準備する事が求められます。適応障害という経験は、デイケア業界における理解深い対応力を身につけた証とも捉える事が出来ます。その経験を活かし、再就職を成功させる為の戦略を立ててみてください。
適応障害での退職を理解し、歓迎するデイケアスタッフの採用理由

面接で適応障害による退職を説明する際、その理由が重要であり、印象を悪くさせないような説明が求められます。
私のケースでは適応障害を引き起こすほどの厳しい労働環境が原因であったと述べ、原因が自身ではなく、職場環境にある事を強調しました。
デイケアセンターではスタッフの人手不足や、高齢者や障害者の増加に伴うケアニーズの高まり等、厳しい現場があります。私の以前の職場では人手不足が常態化しており、一人あたりのケア負担が増えていました。
その結果、一人で多くの利用者のケアを行う事が求められ、一つのミスが大きな問題につながる環境でした。
私の場合、利用者の数が急激に増え、特に認知症の方々のケアが増えました。認知症ケアは、利用者の行動パターンの理解や適切な対応など、専門的な知識と経験が必要です。
しかし人手不足の為に十分な研修や指導が受けられず、自己学習や経験則に頼ってケアを行う事が多くなりました。
もちろん、スムーズにケアが進む事は少なく、利用者やその家族からのクレーム対応、ケアの改善策を見つけるなど、終わりの見えないストレスやプレッシャーが適応障害を引き起こす原因となりました。
このような経験を説明した上で「だからこそ新しい職場ではスタッフの意見を尊重し、十分な研修と指導が受けられる環境を求めています」と述べれば、退職理由や志望動機をうまく伝える事が出来ます。
適応障害で退職した元デイケアスタッフが面接で自己アピールする方法
デイケア職場における適応障害で退職した経験を持つスタッフが、新たな職場を探す際の面接で自己アピールする為の方法を探ります。面接官から「適応障害はあなた自身の問題ではないのか?」と疑われる事もありますが、そのような疑念から自分を守る為の戦略を練りましょう。
面接官は、適応障害が起こった原因が職場環境にあるのか、あるいは個々のスキルや能力に問題があったのかを見極めようとします。「なぜ適応障害を発症し、退職に至ったのか?」その原因をクリアに説明し、自己改善の努力や状況改善の取り組みをアピールする事が重要です。
例えば「ケースロードが過大で、クライアントのニーズに十分に対応出来ない状況が続いた為、適応障害を発症しました。私自身は、上司や同僚に対応方法を相談し、自分のメンタルケアも行っていましたが、組織全体の問題には手が及びませんでした」という具体的な例を出す事が有効です。
また適応障害を経験した事で得た教訓や、その経験を活かしてどのように業務に取り組むつもりなのかを語る事も大切です。例えば「適応障害を経験した事で自分自身の心の健康管理の重要性を痛感しました。新たな職場では自分自身のメンタルケアに配慮しながら、クライアントのケアにも最善を尽くす所存です」と語る事で適応障害を経験した事が今後の職務遂行に対するマイナスではなく、プラスに転じる可能性を示す事が出来ます。
適応障害で退職した経験を持つデイケアスタッフは、自己アピールの方法を工夫し、適応障害の経験を自己成長の一部としてアピールする事が求められます。個々の経験と教訓を活かし、再就職に向けたポジティブなステップを踏み出しましょう。
適応障害が原因でデイケアスタッフが退職する理由と対策
適応障害が原因でデイケアスタッフが退職を余儀なくされるケースがあります。「職場環境や上司が原因で退職する事になった」という訴えがあるかもしれません。しかし適応障害の解消には、自身の問題解決能力をアピールし、改善策を提案する事が肝要です。
適応障害は、職場環境が原因で発症する事が多いですが、それはあなた自身に問題がないとは限りません。ここで重要なのは、自身の問題解決能力と現場が原因で改善されなかった事実を述べる事で「職場を改善するよりも環境を変えた方が良い」、つまり転職が適応障害を解消する一つの手段として捉えられるようになる点です。
具体的な改善策としては以下のような例があります。
- メンバーが急に退職し、引継ぎがなく人員が不足した結果、適応障害に陥りました。この状況を改善する為に、人員の補充や引継ぎ体制の整備を提案します。
- 利用者やその家族間の意見のすれ違いや、急なサービス内容変更が頻繁に起こり、適応障害になりました。ここではコミュニケーション体制の見直しや、サービス提供の透明性を高める提案が有効です。
- 上司が新しいサービスを提案し、業務量が増えた結果、適応障害になりました。このような場合、業務量の管理や、上司との意思疎通の改善を提案します。
上記のような具体的な状況と改善策を明らかにする事で適応障害が悪化し退職に至った経緯を説明する事が出来、新たな職場への就職活動がスムーズに進みます。
適応障害を抱えるデイケアスタッフが退職を選ばない為の工夫

適応障害が原因で退職を考えるデイケアスタッフに対し「当施設で配慮してほしい事は何ですか?」と問われた場合、適応障害による影響を和らげる手法について提案する事が求められます。
適応障害があるという事実から、業務に支障が出るのではないかと疑念を抱かれる事があります。それを払拭する為には、適応障害があっても効率的に業務をこなす為の具体的なアピールと対策が必要となります。
例えば適応障害の発症原因が業務量にある場合、デイケアスタッフでは各種業務を効率化する為にICTを活用する事が考えられます。シフト管理や記録作成、情報共有などをデジタル化し、手間を省く事で業務負担を軽減する事が可能です。
もしくは、職場の人間関係が原因であれば、コミュニケーションツールを活用して、円滑なコミュニケーションを図る事も有効です。またスタッフ間のメンタルサポートを強化し、互いに配慮し合う環境を作る事も重要です。
このように、適応障害を抱えていても効率的に業務をこなす工夫と、その原因を出来るだけ除去する具体的な提案を面接時に述べる事で適応障害という事実を理解し対応出来る職場である事をアピール出来ます。
「なぜ私達の託児所が適応障害にならずに働ける場所だと思ったのですか?」と尋ねられた場合の対処法
適応障害からの回復と共に新たな職場を探す際、託児所の環境が理想とするものであると確信が持てなければならないのですが、面接で「なぜ私達の託児所が適応障害にならずに働ける場所だと思ったのですか?」と尋ねられたとき、答えに詰まる事があります。
適応障害を引き起こさない職場で働く事が必要なので、志望先の託児所の環境が他とは異なる、と主張出来るように準備が必要です。しかしまだその託児所で働いた経験がない為、どのように答えれば良いか迷うかもしれません。私自身は「口コミサイトを見て、あなた方の託児所が一番良いと感じたからです」と回答して問題を解決してきました。
転職を支援するサービスの中には、実際にその託児所で働いた経験のある人々のフィードバックが掲載されているものがあります。私自身このようなサービスを活用してきましたが、求人情報では「充実した休日」と書かれていても、実際に口コミを見ると「休日が多く、仕事量が増え、ストレスが増大した」といったコメントが多い事に気付きました。
このように、実際の職場環境についての評価は、転職先が適応障害を引き起こす可能性のある不適切な環境かどうかを判断する上で非常に有用です。
そして志望動機についても「口コミサイトの評判が良かったから」と述べる事が出来れば、適応障害を持つ自分に適した託児所、または評判が良い託児所であると主張する事が出来ます。したがって、口コミサイトを活用して志望先を選び、志望動機を明確にする事をお勧めします。
適応障害をプラスに変えるデイケアスタッフの対応例
適応障害は一見、デメリットに見えますが、これを適切な対応により、デイケアの現場で活かす事が可能です。
適応障害を持つ利用者の特性を理由に「すみません、行動や発言の記録を取らせてください」と、日々の観察記録を詳細にとる事で利用者の状態把握や変化の把握、またトラブル防止に役立てる事が出来ます。
デイケアの現場ではスタッフ間での情報共有や利用者の状態の把握が非常に重要です。しかし口頭での情報伝達だけでは伝え漏れや情報の歪みが生じてしまう事があります。
そこで適応障害を持つ利用者の対応として、詳細な観察記録を残す事を提案します。これによりスタッフ間での情報共有がスムーズになり、利用者への対応も一貫性を持つ事が出来ます。
また観察記録をとる事で利用者の微細な変化も把握する事が可能となり、早期対応や適切なケアプランの策定につながります。
このように、適応障害を持つ利用者に対する対応を工夫する事で適応障害のデメリットをプラスに変える事が可能です。適応障害を持つ利用者のケアに関わるデイケアスタッフは、このような視点を持つ事が重要と言えます。
適応障害で退職したデイケアスタッフの再就職成功への道
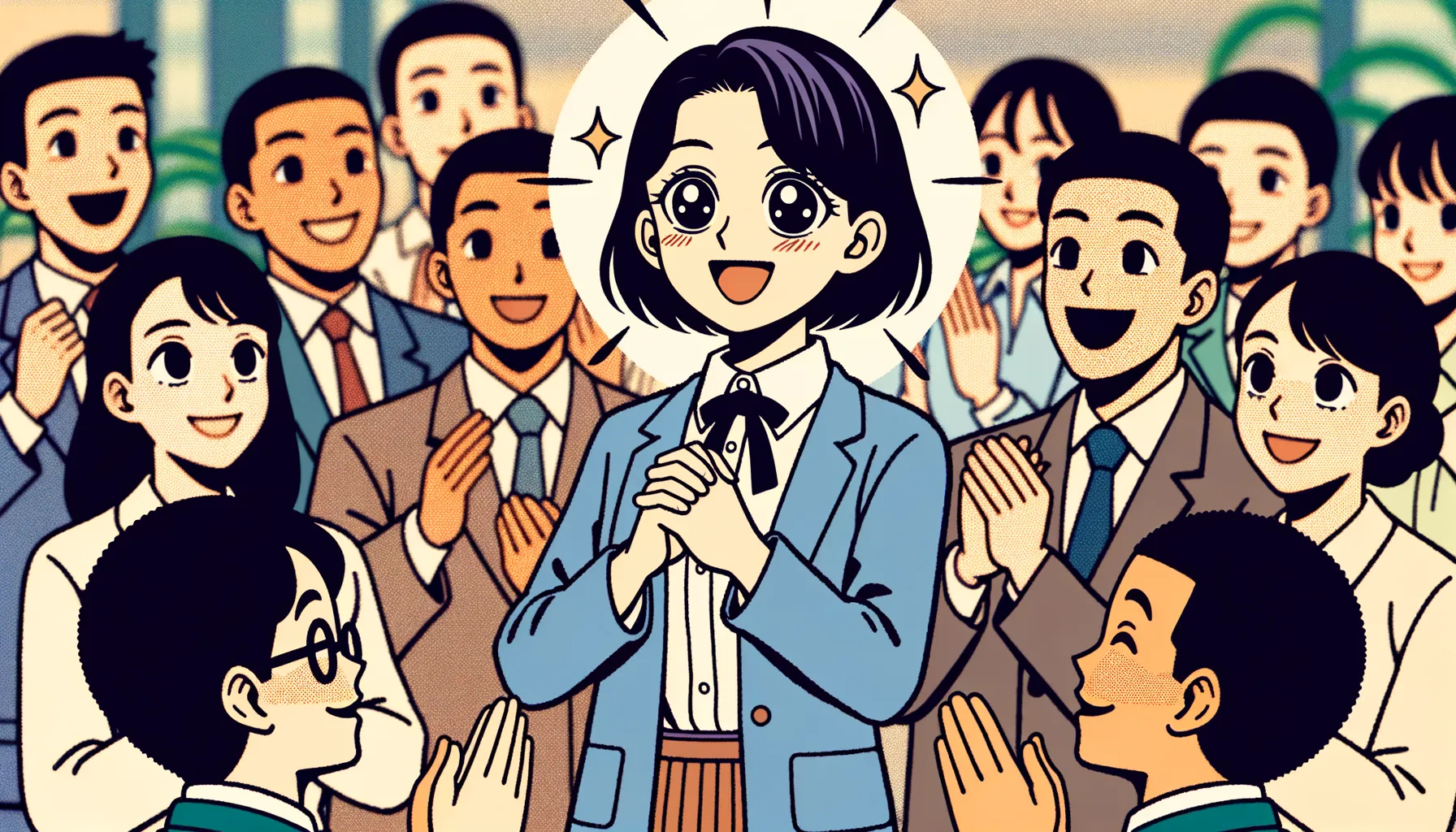
適応障害を理由に退職したデイケアスタッフが再就職を成功させる為には、以下のポイントに注意が必要です。
- 適応障害が退職理由であっても、改善の余地があったとアピールする
- 志望動機として、口コミサイトで評価の高い施設を選ぶ
- 適応障害を逆に長所と捉え、その経験が今後の仕事にどう活かせるかをアピールする
適応障害で退職した場合、失業保険期間は長めに設定すると良いでしょう。精神科医の提案で退職するほど適応障害が深刻であれば、障がい者手帳を申請し、失業保険の期間を一般の3カ月から10カ月に延ばす事が可能です。
また長期間精神科医に通院していた場合、障害年金も受給出来る可能性があります。適応障害で退職した場合でも、日本には障がい者に対するさまざまなサポートがありますので、退職後の期間を活用して手続きを進める事が有益です。
障がい者枠で転職活動を行う場合、障がい者専用の転職サイトでは契約社員の求人が多く、正社員の求人が少ない事に注意が必要です。大手の正社員を障がい者枠で目指すのであれば、直接施設のホームページから応募する事をおすすめします。
正社員採用は競争が激しい為、面接では自分がどのように成果を上げる事が出来るか示す事が大切です。適応障害を逆手にとって、仕事を有利に進める事が出来る話をするなど、障がい者ならではの立ち回りが求められます。
以上が私自身の経験に基づいた、適応障害で退職したデイケアスタッフの再就職成功へのノウハウです。このような工夫を行う事で適応障害を理由に退職したデイケアスタッフでも再就職の成功確率が上がる事を願っています。


